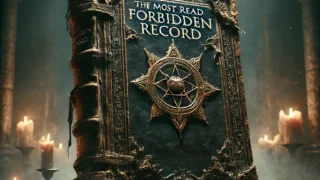昔から日本には、「山には人の住めない領域がある」「山の神様には逆らってはいけない」という言い伝えが残っています。
これは、私が小学生のときに実際に体験した“山の何か”についての話です。
今思い返しても、それが何だったのかははっきりしません。
けれど、あの目の記憶だけは、今でも夏になると夢に出てくるんです。
小学生の頃、毎年夏になると、兄と二人で長野にある祖父の家に一週間ほど預けられていた。
そこは小さな村で、家と家の間には畑と林があり、夜になれば本当に真っ暗になる。
街灯も、車も、人もほとんど通らない。
その年はなぜか、空気が少し違っていた。
祖父はあまり喋らない人だったが、夜になると妙に神経質になり、雨戸をすぐ閉め、部屋の明かりも最小限。「どうして暗くするの?」と聞いても、「そういうもんだ」としか言わなかった。
三日目の夜、寝る前に布団の中で話していたとき、外から「カタン…コツン…」と、何かを叩くような音が聞こえてきた。
最初は枝でも風に揺れてるのかと思ったけど、妙に一定のリズムがあった。
そのとき、兄がぽつりと言った。
「……あれ、“山影様”かもしれない」
“山影様”って何?と聞いたが、兄は答えなかった。
ただ、目だけがずっと天井を見ていたのを覚えてる。
どうしても気になってしまって、四日目の夜、兄が寝たあと、こっそり玄関を出た。
裏手には小さな山に続く道があり、その方向からあの音が聞こえていた。
「カタン…カタン…」
音を頼りに林の手前まで来たとき、急にピタリと音が止んだ。
風もなくなり、虫の声もしない。不自然なくらい静かだった。
そのとき、山道の先に“何か”がいた。
人の背丈ほどある黒い影。輪郭がぼやけていて、煙のように揺らいでいる。
目のような赤い点がふたつ、こちらをじっと見ていた。
声も出せず、身体が固まって動けなかった。
「やばい」と思った瞬間、後ろから腕をつかまれた。
祖父だった。
無言で俺を引っ張って走った。振り返ると、“それ”は道の真ん中に立ったまま、動いていなかった。
追ってくる気配もなく、ただ立っていた。
家に戻ると、祖父は何も言わなかった。
次の日、近くの小さな寺に連れて行かれ、坊さんの前で何かを読まれた。意味はわからなかったけど、真剣な空気だった。
その後、音は聞こえなくなった。
祖父はもう亡くなっているし、あの村にも何年も行っていない。
ただ、あの“赤い目”だけは今でもはっきり覚えてる。夢にも、夏になるとたまに出てくる。
“山影様”が妖怪だったのか、土地に根付いた何かだったのかは分からない。
ただ、夜の山道だけは、今も怖くて歩けない。
あのとき、もう少しで見てしまうところだった気がするから。
【おまけ】“山の妖怪”にまつわる話
日本各地には、山に住む“何か”の話がいくつも残されています。
- 名前を呼んではいけない存在
- 夜に音で気を引こうとするもの
- 姿を見ると戻ってこられない者
それらは「妖怪」や「神様」として語られることもありますが、どこか共通する“得体の知れなさ”があります。
もしも、山道で誰もいないのに音が聞こえたら。
それは、誰かがそこにいるのではなく、“何か”がこちらを見ているのかもしれません。